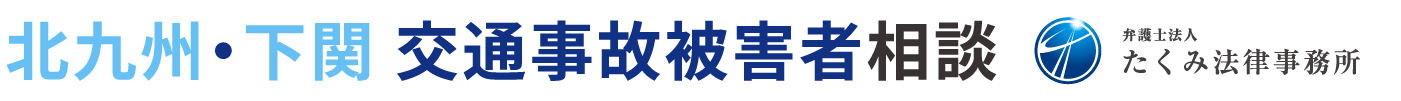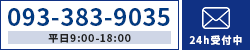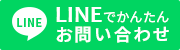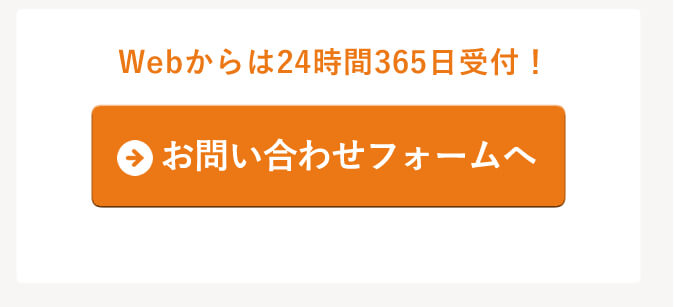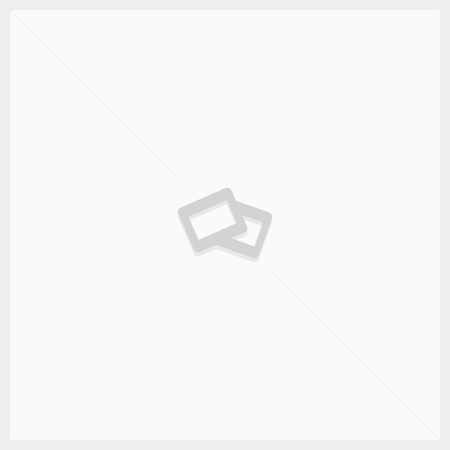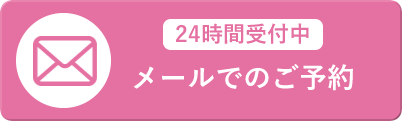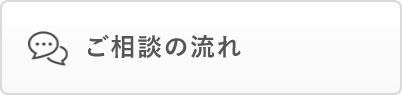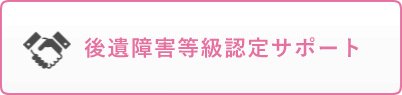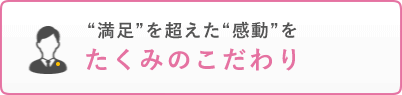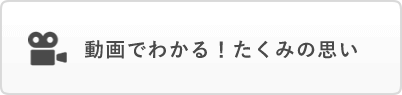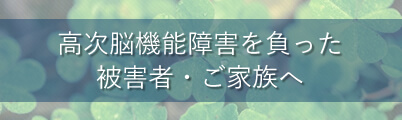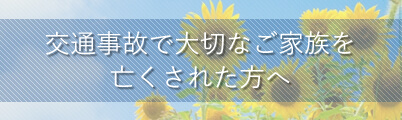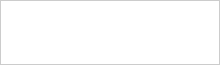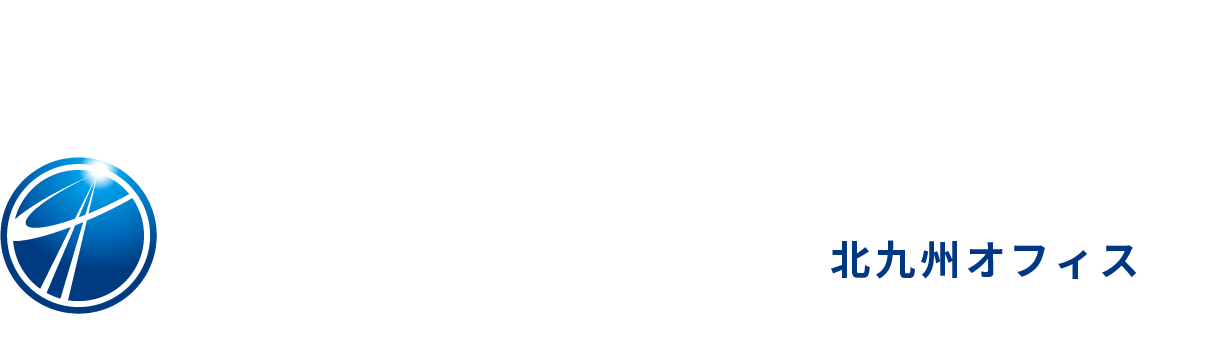| 相談者 | 男性(20代) / 福岡市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 事故態様 | バイク対車 |
| 後遺障害 | 併合6級 |
| サポート結果 | ・高次脳機能障害認定 ・保険会社との示談交渉で約9,000万円が認定 |
主な損賠項目と賠償金額
| 総賠償額 | 約9,000万円 |
|---|
相談・依頼のきっかけ

福岡市にお住まいの20代の会社員の男性が、バイクで交差点を直進していたところ、右折してきた車と衝突する交通事故に遭いました。
事故後は通院を続けていましたが、相手方保険会社から治療費の打ち切りを示唆され、症状固定後の後遺障害等級がどのように認定されるか不安を感じておられました。
今後の手続きや対応について弁護士にアドバイスしてほしいとのことで、当事務所にご相談いただきました。
当事務所の活動
男性が当初取得していた後遺障害診断書には、高次脳機能障害に関する所見の記載が十分ではありませんでした。
多くの医師は、後遺障害の等級認定を意識せず診断書を作成することがあるため、このまま相手方保険会社を通じて後遺障害申請を行うと、適切な後遺障害が認められないおそれがありました。
そこで当事務所では、相手方保険会社経由ではなく、被害者請求の方法で後遺障害申請を行う方針をとりました。
当事務所が関与した結果
男性やご家族、主治医の協力を得ながら、後遺障害を立証するための資料を丁寧に収集し、以下の書類を整えて自賠責保険会社および損害調査事務所へ提出しました。
- 事故後の意識障害の程度報告書
- 専門医による脳の画像および診断書
- 心理・知能検査結果
- 詳細な日常生活状況報告書
これらの資料により、男性に残った高次脳機能障害の実態を的確に裏付けました。
その結果、高次脳機能障害について後遺障害7級が認定され、他の障害と合わせて併合6級という結果を得ることができました。
後遺障害が認定された後、相手方保険会社との示談交渉において、弊所の提出資料や主張が大きく評価されました。
異議申立てや裁判を行うことなく、請求額に近い約9,000万円の賠償金で早期の解決に至り、男性にも大変ご満足いただく結果となりました。
弁護士の所感(活動のポイント)
高次脳機能障害の後遺障害等級を適正に認定してもらうためには、通常の診断書だけでは不十分です。
診断書に記載される内容は非常に重要であり、書面審査によって判断されるため、記載の有無によって数千万円単位で補償額が変わることもあります。
そのため、医師やご家族と連携し、被害者の生活実態や症状を正確に伝える書類を整えることが何より重要です。
今回のように弁護士が医師と協議しながら診断書の方向性を整理したことで、適切な等級認定と十分な補償を受けることができました。
高次脳機能障害は一見わかりにくい障害ですが、立証の工夫次第で結果は大きく変わると改めて感じました。
高次脳機能障害で適切な等級認定を受けるためのポイント
高次脳機能障害は、見た目の外傷が少なくても、記憶力・集中力・判断力などに影響が出ることが多い障害です。
そのため、被害者自身や家族であっても、日常生活の変化を「後遺症」として適切に伝えることが難しい場合があります。
適切な等級認定を受けるためには、次のような点を意識することが重要です。
早期から専門医に相談すること
脳神経外科やリハビリ科など、高次脳機能障害に詳しい医師に診てもらうことで、検査や診断の精度が高まります。
家族の観察記録を残すこと
被害者の日常生活での変化(物忘れ、感情の起伏、社会的行動の変化など)を、家族が具体的に記録しておくと、診断書や日常生活報告書の作成時に役立ちます。
弁護士と医師が連携して資料を作成すること
後遺障害等級は「書面審査」で決まるため、診断書や検査結果の内容が極めて重要です。
弁護士が医師と協議し、検査や記載内容を適切に整えることで、認定結果が大きく変わることがあります。
高次脳機能障害は、見えにくい障害だからこそ、立証の工夫と準備が欠かせません。
事故後に「何かおかしい」「以前と様子が違う」と感じたら、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
関連ページ