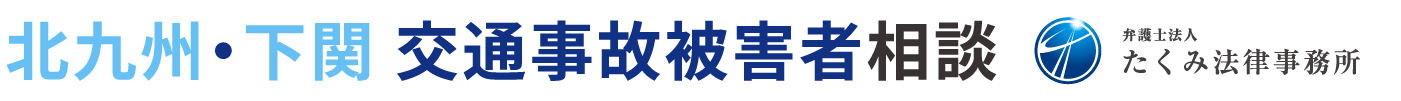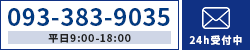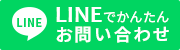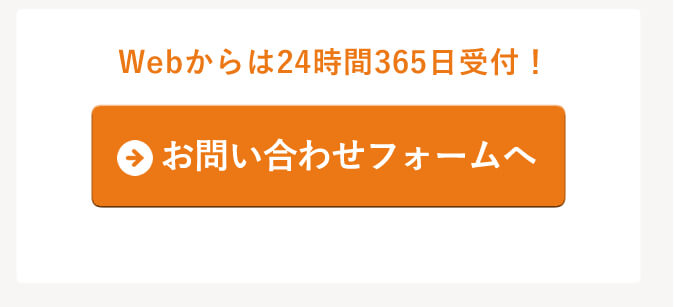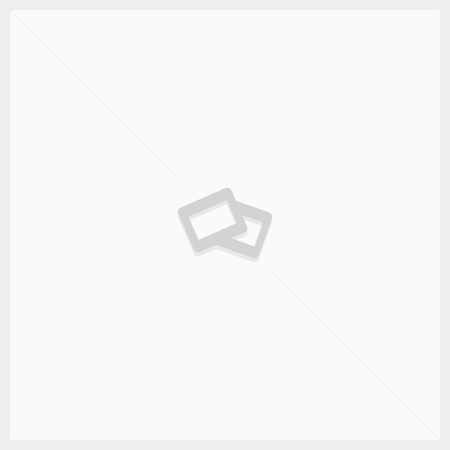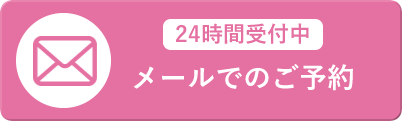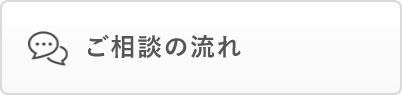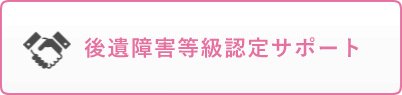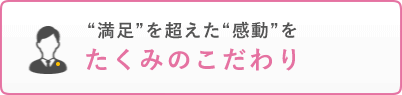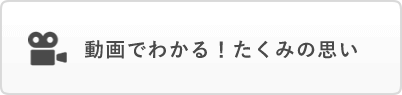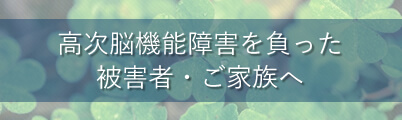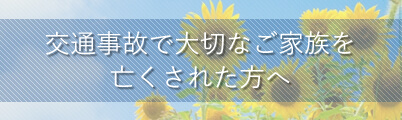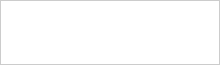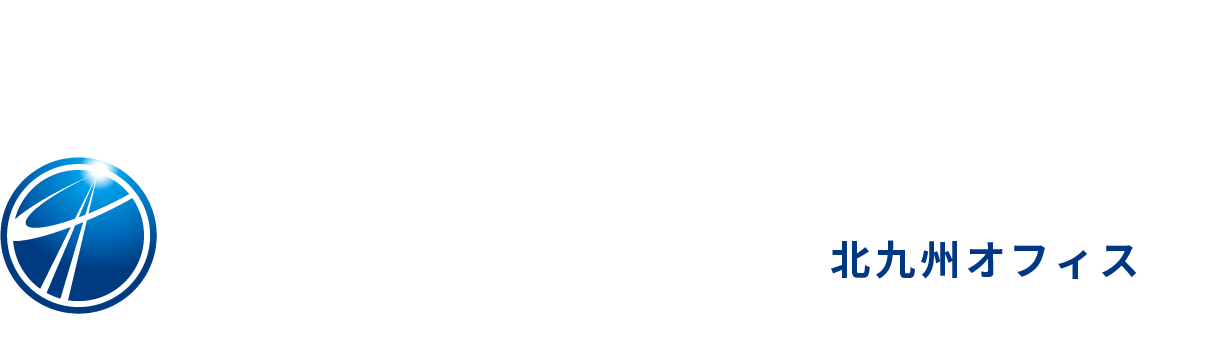| 相談者 | 男性(40代) / 福岡市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 事故態様 | 歩行者対車 |
| 傷病名 | 左上腕骨近位端骨折、第5腰椎破裂骨折、右恥坐骨骨折、多発顔面骨折、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、右閉瞼不全、外傷性嗅覚障害 |
| 後遺障害 | 併合8級 |
| サポート結果 | ・後遺障害等級認定サポートにより併合8級認定 ・過失割合15%→5% |
主な損賠項目と賠償金額
| 後遺障害慰謝料 | 約747万円 |
|---|---|
| 後遺障害逸失利益 | 約2237万円※1 |
| 傷害慰謝料 | 約324万円 |
| 休業損害 | 約708万円 |
| 合計 | 3819万円 |
※2 自賠責保険金819万円含む
相談・依頼のきっかけ

福岡市在住の40代男性が、信号のない横断歩道を歩行中、黄色点滅信号で進行してきた車にはねられるという重大事故に遭いました。
男性はその場で救急搬送され、左上腕骨近位端骨折、第5腰椎破裂骨折、右恥坐骨骨折、多発顔面骨折、外傷性くも膜下出血など、複数の重傷と診断されました。
4か月の入院治療を経て退院した後も、通院リハビリや複数回の手術が必要な状態が続きました。
事故から1年半ほどが経過した頃、主治医や保険会社から「症状固定」の話が出たことをきっかけに、今後の対応や後遺障害申請について相談したいとのことで、弊所にご依頼いただきました。
たくみ法律事務所の活動
男性には治療に集中していただき、当事務所では定期的に治療経過を確認しながら、後遺障害申請のタイミングや方針を慎重に検討しました。
今回の事故で、脳神経外科・眼科・整形外科・形成外科・耳鼻科の5つの診療科に通院されており、それぞれで症状が残っていました。
そのため、すべての診療科で後遺障害診断書を作成していただき、弁護士が内容を精査しました。
診断書の記載に不足がある場合は、医師と連携して追記を依頼し、後遺障害認定に必要な医学的資料を整えたうえで被害者請求を行いました。
たくみ法律事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、以下の等級が認定されました。
| 高次脳機能障害 | 9級10号 |
|---|---|
| 左肩関節の機能障害 | 10級10号 |
| 脊柱の変形障害 | 11級7号 |
| 外貌の醜状障害 | 12級14号 |
| 嗅覚障害 | 14級 |
これらを併せて、併合8級が認定されました。
その後の相手方保険会社との示談交渉では、「逸失利益」と「過失割合」が争点となりました。
相手方は当初、労働能力喪失率20%、逸失利益1,278万円が妥当と主張していましたが、残存症状による就労制限の実態を丁寧に立証し、最終的に労働能力喪失率35%、逸失利益2,237万円まで増額することができました。
また、過失割合についても、刑事記録をもとに粘り強く交渉を重ねた結果、相手方が主張していた15%から5%まで下げることに成功しました。
最終的に、自賠責保険金819万円に加えて、相手方保険会社から約3,000万円の補償が認められ、ご依頼者様にも納得いただいたうえで示談が成立しました。
弁護士の所感(活動のポイント)
本件は、多発骨折や高次脳機能障害など、極めて重い後遺障害を伴う事案でした。
治療やリハビリの長期化に加え、複数の診療科にわたる後遺障害申請が必要であり、弁護士による総合的なサポートが欠かせませんでした。
重傷事案では、医師との連携や診断書の内容確認、そして症状の裏付け資料の準備が、後遺障害認定や賠償金額に大きく影響します。
また、交渉にあたっては、労働能力喪失率や過失割合の主張立証が結果を左右します。
今回、最終的に高額な補償を実現できたのは、医学的・法的双方の観点から一貫して丁寧に対応できた点が大きな要因といえます。
重傷事故で将来に不安を抱えている方は、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。
高次脳機能障害で適切な等級認定を受けるためのポイント
高次脳機能障害は、見た目の外傷が少なくても、記憶力・集中力・判断力などに影響が出ることが多い障害です。
そのため、被害者自身や家族であっても、日常生活の変化を「後遺症」として適切に伝えることが難しい場合があります。
適切な等級認定を受けるためには、次のような点を意識することが重要です。
早期から専門医に相談すること
脳神経外科やリハビリ科など、高次脳機能障害に詳しい医師に診てもらうことで、検査や診断の精度が高まります。
家族の観察記録を残すこと
被害者の日常生活での変化(物忘れ、感情の起伏、社会的行動の変化など)を、家族が具体的に記録しておくと、診断書や日常生活報告書の作成時に役立ちます。
弁護士と医師が連携して資料を作成すること
後遺障害等級は「書面審査」で決まるため、診断書や検査結果の内容が極めて重要です。
弁護士が医師と協議し、検査や記載内容を適切に整えることで、認定結果が大きく変わることがあります。
高次脳機能障害は、見えにくい障害だからこそ、立証の工夫と準備が欠かせません。
事故後に「何かおかしい」「以前と様子が違う」と感じたら、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
関連ページ